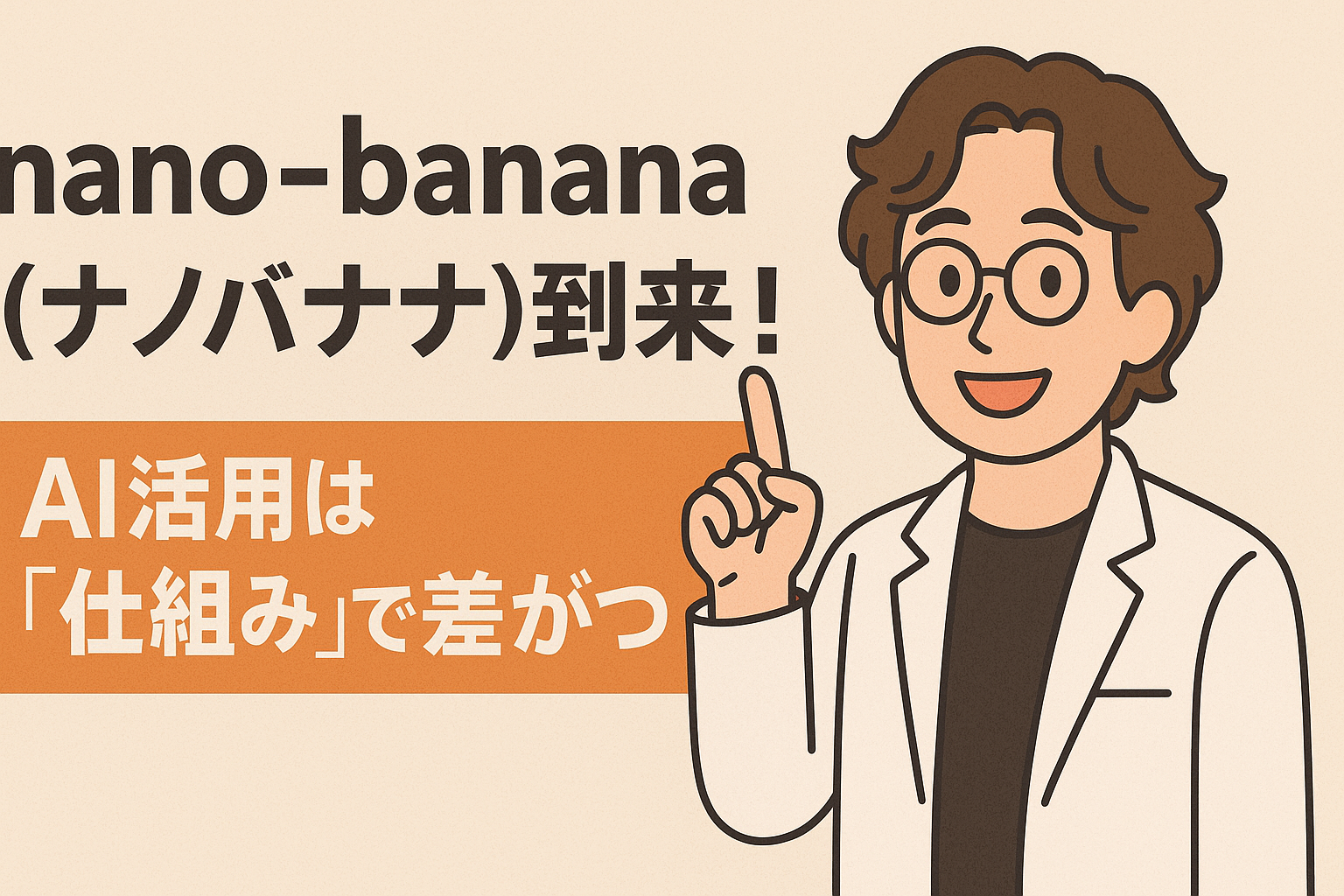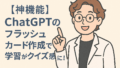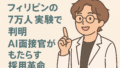AIに関する情報発信や業務効率化のサポートをしているフリーランスのナオキです。
皆さんは、普段どのようにAIを使っていますか。多くの方が、インターネットに接続して特定のウェブサイトやアプリを開いて利用しているのではないでしょうか。しかし、そんなAIの使い方が大きく変わるかもしれない、そんな未来を予感させるニュースが飛び込んできました。
今回は、Googleが開発中と噂されている新しい小型AI「nano-banana(ナノバナナ)」の話題をきっかけに、これからのAIとの付き合い方、そして私たちの仕事がどう変わっていくのかについて、一緒に考えていきたいと思います。
スマホでAIがサクサク動く未来?オンデバイスAIの可能性
今回注目されている「nano-banana」というAIは、その名前から非常に小さいモデルであることが想像できます。Googleはこれまでも「Gemma」シリーズなどで、「ナノ」という名前を冠した比較的小さなAIモデルを、開発者向けに提供してきました。
これらの小さなAIモデルが目指しているのは、「オンデバイスAI」という考え方の実現です。
皆さんが今使っているChatGPTなどのAIは、質問をインターネット経由で巨大なデータセンターにある高性能なコンピュータ(サーバー)に送り、そこで処理された答えが返ってくる「クラウドAI」という仕組みです。これは非常に賢いAIを使える反面、インターネット接続が必須ですし、たくさんの人が同時に使うと少し反応が遅くなることもあります。
一方、「オンデバイスAI」は、その名の通り、皆さんがお持ちのスマートフォンやパソコンといった端末(デバイス)の中で、AIが直接動く仕組みを指します。インターネットを介さず、手元の機械の中だけでAIが完結するイメージですね。
もし、このオンデバイスAIが普及したら、私たちの日常や仕事はどう変わるのでしょうか。
まず考えられるのは、圧倒的なスピードです。インターネットを経由しないため、AIの応答が非常に速くなります。まるでスマホにもともと入っている電卓アプリのように、瞬時に答えが返ってくるようになるかもしれません。
次に、オフラインでも使えるという大きなメリットがあります。電波の届かない飛行機の中や地下鉄での移動中でも、AIアシスタントに相談したり、文章を作成してもらったりすることが可能になります。これは、場所を選ばずに仕事をする私たちフリーランスや経営者にとっては、非常に心強い味方になるはずです。
さらに、プライバシーやセキュリティの観点からも安心感が増します。自分のスマホの中で情報が処理されるため、機密性の高い顧客情報や社内データを、外部のサーバーに送ることなくAIで分析・活用できる可能性が広がります。
皆さんも少し想像してみてください。もしインターネットに繋がっていなくても、手元のスマホの中だけで高度なAIが動いてくれるとしたら、どんな新しい仕事の進め方ができるでしょうか。
AI活用の主役は「AIそのもの」から「仕事の仕組み」へ
オンデバイスAIが普及すると、AIは特別なサービスというより、スマホのカメラやGPS機能のような「当たり前の部品」になっていくでしょう。そうなると、AI活用の価値は、どのAIを使うかという「AIモデルの選択」から、「AIをどう仕事に組み込むか」という「仕事の仕組み(ワークフロー)の設計」へと移っていきます。
言葉だけだと少し難しいかもしれませんので、具体的な例を挙げてみましょう。
例えば、ある営業担当者のワークフローを考えてみます。今までは、お客様と名刺交換をしたら、会社に戻ってから手作業で顧客管理システム(CRM)に入力し、お礼のメールを書いていました。
これがオンデバイスAIの時代になると、こう変わるかもしれません。
- スマホのカメラで名刺を撮影する。
- 端末内のAIが瞬時に文字を認識し、会社名や氏名、連絡先を自動で抽出する。
- そのまま顧客管理アプリに情報を自動登録する。
- さらにAIが、過去のやり取りや今回の面談内容の簡単なメモをもとに、相手に合わせたお礼メールの文案を3パターンほど自動で作成してくれる。
- 担当者はその中から最適なものを選んで、少し手直しするだけで送信完了。
この一連の流れが、すべてスマホ一台で、しかもオフラインの移動中にでも完結するのです。これは単にAIでメールを書くだけでなく、名刺の読み取りから顧客登録、メール作成までを連携させた「仕事の仕組み」そのものですよね。このような、AIを組み込んだ効率的なワークフローを考え出し、実行できるかどうかが、ビジネスの生産性を大きく左右する時代になるのです。
SNS運用でも同じです。外出先で撮った一枚の写真から、AIがターゲット層に響く投稿文のキャッチコピーや本文を複数提案し、関連性の高いハッシュタグまで自動で生成してくれる。そんなワークフローがあれば、コンテンツ制作の時間を大幅に短縮できます。
AIを作る時代から、AIを使いこなす時代へ
ここまで読んで、「AIを組み込んだワークフローが大事なのは分かったけど、そんな仕組みを自分で作るのは難しそうだ」と感じた方もいるかもしれません。
確かにその通りですが、ここで重要な視点があります。それは、私たちは「AIをゼロから作る必要はない」ということです。
現在、GoogleやOpenAI、Microsoftといった巨大IT企業が、莫大な資金と人材を投じて、超高性能なAIモデルの開発競争を繰り広げています。その進化のスピードは凄まじく、中小企業や個人事業主が自前で同等のAIを開発するのは、現実的に不可能です。
だからこそ、私たちの役割は、彼らが提供してくれる優れたAIという「最高の道具」を、いかに自分の仕事に合わせて使いこなすか、という点に集約されていきます。
そこで、ますます重要になってくるのが「プロンプトエンジニアリング」のスキルです。プロンプトエンジニアリングとは、簡単に言えば「AIへの上手な指示出しの技術」のことです。
AIは非常に賢いですが、私たちの意図を完璧に察してくれるわけではありません。期待通りの成果物を得るためには、「あなたはプロのマーケターです」「以下の情報を基に、30代女性向けの親しみやすい口調でブログ記事を書いてください」といったように、AIに役割を与え、背景情報を伝え、具体的な指示を出す必要があります。
先ほど例に挙げた営業担当者のワークフローでも、各段階で「名刺からこの項目を抽出して」「この顧客情報をもとに、丁寧かつ簡潔なお礼メールを作成して」といった的確な指示、つまりプロンプトが必要になります。
これからの時代に求められるのは、プログラミングのように複雑なコードを書く能力よりも、自分の業務を深く理解し、それをAIが理解できる言葉に翻訳して、一連の作業として組み立てる能力なのです。
まとめ
Googleの「nano-banana」の噂は、単なる新しい技術の登場を意味するだけではありません。それは、AIがクラウドの向こう側にある特別な存在から、私たちの手元にある身近なパートナーへと変わっていく、大きな時代の転換点を示唆しています。
この変化の波に乗り遅れないために、私たちが今からできることは何でしょうか。それは、まずAIに触れてみることです。そして、「自分の仕事のこの部分、AIを使えばもっと楽になるかもしれない」と考える癖をつけることです。
AIを作るのは巨大企業の役目だとしても、AIをどう活かすかというアイデアは、現場で働く私たちの中にこそ眠っています。自社の業務に最適なワークフローを設計し、的確な指示でAIを動かすスキルを磨いていくこと。それが、これからの時代を生き抜くための、新しい標準スキルになっていくのかもしれません。
皆さんのビジネスでは、どんなAIワークフローが作れそうでしょうか。ぜひこの機会に、未来の働き方を想像してみてください。