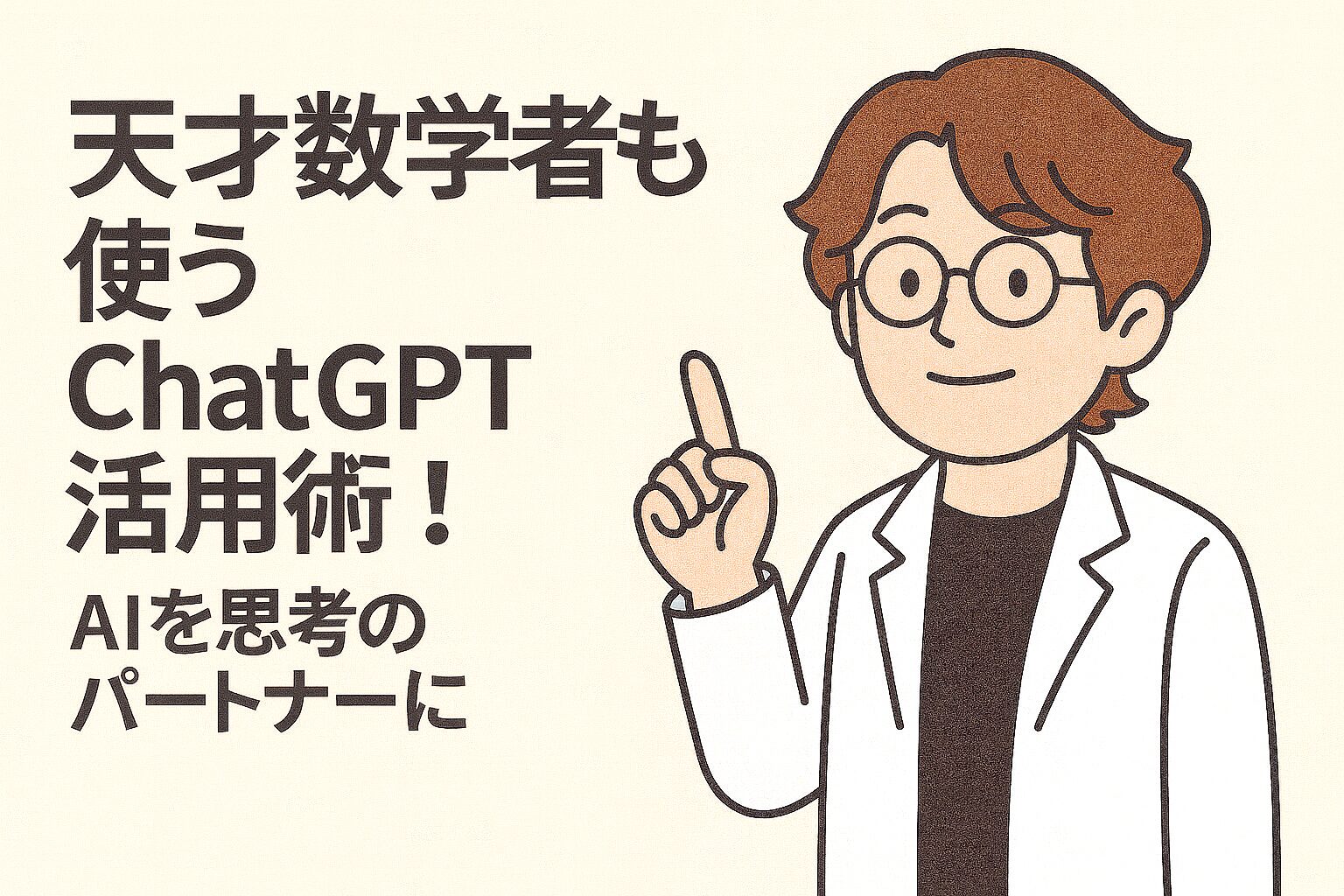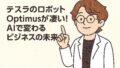AI活用の専門家ナオキです。フリーランスとして、AIを使った業務効率化やSNS運用のお手伝いをしています。
最近、AIの進化には目を見張るものがありますよね。SNSを見れば毎日のように新しいAIツールが登場し、「これもAIでできるようになったのか」と驚かされることばかりです。
そんな中、先日「数学界の天才がChatGPTを使って難問を解いた」というニュースが飛び込んできました。今日はこの驚きの事例をご紹介しながら、私たち個人事業主や中小企業経営者が、AIをビジネスにどう活かせるか、そのヒントを探っていきたいと思います。
天才数学者はAIをどう使ったのか?
今回、AIを活用して数学の難問解決に挑んだのは、テレンス・タオ教授という数学界では世界的に有名なトップランナーです。フィールズ賞という、数学のノーベル賞とも言われる賞を受賞している、まさに「天才」です。
そんなタオ教授が、自身の立てた理論が本当に正しいかを検証するために、ChatGPTを使ったというのです。具体的には、その理論が成り立たないケース、つまり「反例」を探し出すという課題でした。
膨大な計算からの「方針転換」
最初、タオ教授は反例を見つけるために、コンピューターに自動で計算させるプログラムを組んで探そうとしました。しかし、考えられる組み合わせが膨大すぎて、計算に途方もない時間がかかってしまうことがわかったのです。いわば、砂漠の中からたった一粒の特定の砂を探すような作業だったのかもしれません。
そこで教授は方針を転換します。力ずくで探すのではなく、AIと対話しながら、より効率的に答えに近づいていく方法を選んだのです。これは、私たちの日々の業務にも通じるものがありますよね。一つのやり方で行き詰まったとき、別のツールやアプローチを試してみる。その選択肢の一つに、AIとの「対話」が入ってきた時代なのだと感じます。
AIは優秀な「壁打ち相手」だった
タオ教授はChatGPTに対して、段階的に質問を投げかけ、条件を少しずつ絞り込んでいきました。驚くべきは、AIが教授の専門的で高度な意図を正確に理解し、的確な応答を返したことです。
対話の途中、教授の考えに数学的な間違いがあった際には、AIがそれをやさしく指摘し、修正案を提示することまであったそうです。まるで、優秀な研究パートナーと議論を重ねるように、AIとの対話を通じて思考を深め、正しい方向へと進んでいったのです。
最終的に、AIとの協力によって導き出された条件は、わずか29行の短いプログラムコードで検証できるものでした。そして見事、探していた反例を発見することに成功したのです。タオ教授自身も、この取り組みによって大幅な時間短縮ができたと高く評価しています。
タオ教授に学ぶ!明日から使えるAIとの付き合い方3つのヒント
この話を聞いて、「天才数学者だからできたことで、自分には関係ない」と感じた方もいるかもしれません。でも、そんなことはありません。タオ教授のAI活用術には、私たちのビジネスを加速させるための重要なヒントがたくさん隠されています。
ヒント1:思考の整理とアイデア出しの「相談相手」として使う
あなたは、新しいサービスの企画やキャンペーンのアイデアを考えるとき、一人で考えていませんか。タオ教授がAIと対話しながら思考を整理したように、私たちもAIを「壁打ち相手」として活用できます。
例えば、こんな風に話しかけてみてください。
「カフェの新しい集客イベントのアイデアを5つ提案して」
「30代女性向けの新しい化粧品のキャッチコピーを考えて」
「この事業計画の弱点はどこだと思う?」
AIは、自分では思いつかなかった視点や切り口を提供してくれます。もちろん、出てきた答えがすべて完璧なわけではありません。しかし、そのアイデアをたたき台にして自分の考えを深めていくことで、一人で悩むよりもずっと早く、質の高い結論にたどり着けるはずです。
ヒント2:時間のかかる作業を任せて「時短」を実現する
タオ教授は、膨大な時間がかかる計算作業をAIとの対話でショートカットしました。私たちも、日々の業務に潜む「時間がかかるけれど、単純な作業」をAIに任せることができます。
例えば、市場調査のための情報収集や、顧客アンケートの結果の要約、SNS投稿の文章作成などです。僕自身も、クライアントへの提案資料を作る際、競合他社の動向リサーチの一部をAIにお願いすることがあります。そのおかげで、最も重要な提案の戦略部分を練ることにじっくりと時間をかけられるようになりました。
あなたも、「この作業、誰かに任せられたら楽なのに」と感じる業務はありませんか。その「誰か」の役割を、AIが担ってくれるかもしれません。
ヒント3:苦手分野を補う「スーパーアシスタント」として使う
タオ教授は数学の専門家ですが、AIはプログラミングコードの生成という形で彼をサポートしました。このように、AIは私たちの専門外の領域や苦手な分野を補ってくれる強力なアシスタントになります。
例えば、個人事業主の方なら、簡単なウェブサイトの修正に必要なコードを書いてもらったり、海外の取引先へのメール文を作成してもらったりすることも可能です。契約書の内容を読み込ませて、「この契約で注意すべき点を分かりやすく要約して」とお願いすることもできるでしょう。
ただし、一点だけ注意が必要です。AIはまだ完璧ではありません。特に法律や金融など専門的な分野では、AIが出した答えを鵜呑みにせず、必ず専門家に確認したり、自分自身で最終チェックを行ったりすることが重要です。AIを便利なアシスタントとして使いつつ、最後の判断は人間が下すという姿勢が大切です。
AIは思考のパートナー。まずは小さな一歩から
テレンス・タオ教授の事例は、AIが単なる作業を自動化するツールではなく、私たちの思考を助け、共に問題解決を目指す「パートナー」になり得ることを示してくれました。
この強力なパートナーを、一部の専門家や大企業だけのものにしておくのはもったいないと思いませんか。私たちのような個人事業主や中小企業こそ、AIを味方につけることで、限られたリソースの中で大きな成果を生み出すことができるはずです。
まずは難しく考えず、今あなたが使っているパソコンやスマホから、無料のAIツールに何か一つ質問をしてみてください。「今日のブログのタイトル案を考えて」でも、「お客様への感謝を伝えるメールの文面を作って」でも、何でも構いません。
その小さな一歩が、あなたのビジネスを大きく変えるきっかけになるかもしれません。今日の記事が、あなたがAIという強力な味方を迎えるきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。
AIの活用について、もし何かお困りのことがあれば、いつでも気軽に声をかけてくださいね。

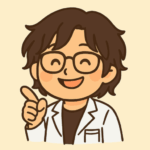
監修者:岡田 直記
AIコンサルント / 「ナオキのAI研究所」所長
企業のAI活用を支援するAIコンサルタント。セミナーや法人研修、個人指導などを通じ、これまでに延べ100名以上へAI活用の指導実績を持つ。現在は、主に中小企業を対象としたAI顧問として、業務効率化や生産性向上を実現するための戦略立案からツール導入までをサポート。また、個人向けには月額制の「AI家庭教師」サービスを展開し、実践的なAIスキルの習得を支援している。
自身の「元大手営業マンでスキル0から独立した」という異色の経歴を活かし、ビジネスの現場目線と最新のAI知識を組み合わせた、具体的で分かりやすい解説が強み。AI技術がもたらす未来の可能性を、一人でも多くの人に届けることを mission としている。