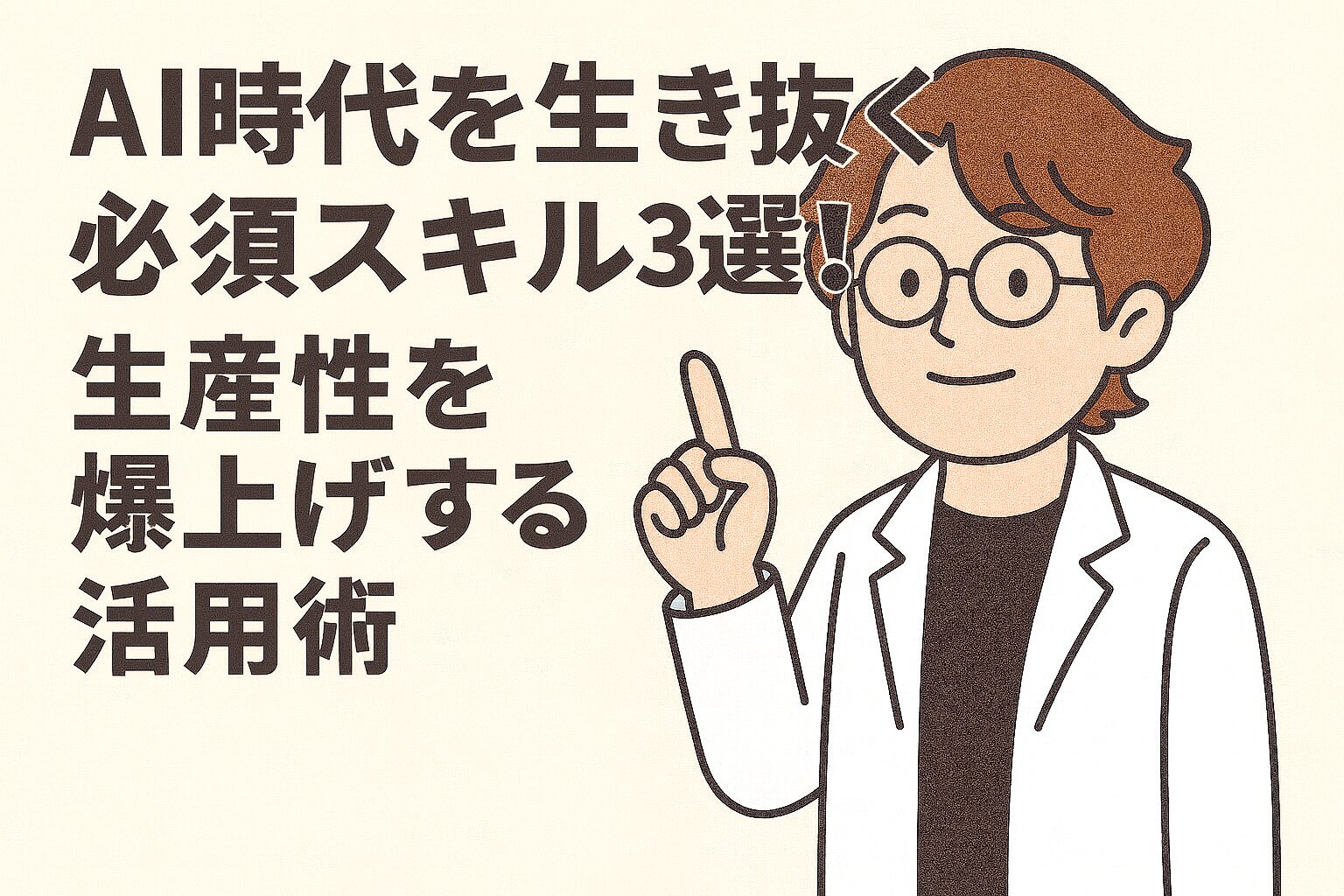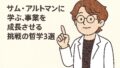AI活用コンサルタントのナオキです。
最近、生成AIの話題を耳にしない日はない、というくらい盛り上がっていますね。皆さんの周りでも「ChatGPTを使ってみた」「画像生成AIがすごい」といった会話が増えているのではないでしょうか。AIを導入すれば、面倒な作業が自動化され、誰でも簡単に生産性を上げられる。そんな夢のような未来を想像している方も多いかもしれません。
しかし、現実はもう少し複雑なようです。最近、アメリカの経済紙ウォールストリートジャーナルで、非常に興味深い記事が掲載されました。それは「AIの普及が、職場で新しい能力の格差を生み出している」という内容です。
今日はこの「AI格差」というテーマについて、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。これは、これからの働き方を左右する、とても重要な問題です。
AIが引き起こす「生産性の差」とは?
記事によると、AIをうまく使いこなせる人とそうでない人の間で、仕事の生産性に驚くほどの差が生まれているそうです。同じAIツールを使っているにもかかわらず、ある人は数時間かかっていた作業を数分で終わらせる一方で、別の人は思ったような成果が出せずに時間を浪費してしまう。そんな状況が、多くの職場で起こり始めています。
例えば、新しいサービスの企画書を作成する場面を想像してみてください。
AIを使いこなせるAさんは、AIに的確な指示を出し、市場調査の要約、ターゲット顧客の分析、企画の骨子などを瞬時に生成させます。そして、AIが作成したたたき台をもとに、自身の経験と知識を加えて、わずか1時間で質の高い企画書を完成させました。
一方、AIに慣れていないBさんは、どう指示すれば良いかわからず、曖昧なお願いをしてしまいます。返ってくるのは、ありきたりで的外れな回答ばかり。結局、AIを使うのを諦めて、従来通りゼロから情報収集を始め、企画書を完成させるのに丸一日かかってしまいました。
これは極端な例に聞こえるかもしれませんが、現実に起こっていることです。AIという同じ道具を手にしても、その使い方一つで、仕事のスピードと質に天と地ほどの差が生まれてしまうのです。では、この差は一体どこから来るのでしょうか。
格差を生む3つのポイント
AIを使いこなせる人とそうでない人の違いは、決してパソコンスキルの有無だけではありません。そこには、AI時代特有の、新しい能力が関係しています。ポイントは大きく分けて3つあります。
的確な指示を出す力(プロンプト力)
まず一つ目は、AIに「的確な指示を出す力」です。これはプロンプトと呼ばれ、簡単に言えば「AIへのお願いの仕方」のことです。
AIは魔法の杖ではありません。私たちが何をしてほしいのかを具体的に、分かりやすく伝えてあげないと、期待通りの仕事はしてくれません。
例えば、「面白いブログ記事を書いて」とお願いするだけでは、AIは何について、誰に向けて、どんな雰囲気で書けばいいのか分からず、ぼんやりとした文章しか返ってきません。
一方で、「あなたは中小企業の経営者に向けたビジネスブログの専門家です。AI活用による業務効率化をテーマに、読者がすぐ試したくなるような具体的な事例を3つ含めて、親しみやすい口調で1500字程度の記事を書いてください」とお願いすれば、AIは役割を理解し、より精度の高い文章を生成してくれます。
私も最初は、この指示出しに苦労しました。「なんでこんな答えしか返ってこないんだ」とイライラしたこともあります。しかし、試行錯誤を繰り返すうちに、AIとの対話のコツが掴めてきました。どう質問すれば、AIが持っている能力を最大限に引き出せるか。この対話力こそが、生産性を左右する最初の関門なのです。
情報の真偽を見抜く力(ファクトチェック力)
二つ目は、AIが生成した情報が本当に正しいかを見抜く力です。AIは時々、事実とは異なる、もっともらしい嘘をつくことがあります。この現象は「ハルシネーション」と呼ばれています。AIは膨大なデータから学習していますが、その情報が全て正しいとは限りませんし、文脈を完璧に理解しているわけでもないのです。
例えば、市場調査レポートの作成をAIに依頼した際に、架空の企業名や存在しない統計データを、さも事実であるかのように記述してくることがあります。その分野に関する専門知識がないと、この嘘に気づかず、誤った情報をもとに重要な経営判断をしてしまうかもしれません。
AIが出してきた答えを鵜呑みにせず、「これは本当に正しい情報か」「根拠となるデータは何か」と一度立ち止まって考える批判的な視点。そして、その内容を検証するための専門知識。この二つがなければ、AIは便利なアシスタントどころか、ビジネスを混乱させる危険な存在にもなり得ます。
生成された情報を応用する力(編集・活用力)
三つ目は、AIが生成したものを「素材」として捉え、自分の仕事に活かす応用力です。AIが作成した文章やデータは、あくまでたたき台であり、完成品ではありません。
先ほどの企画書の例で言えば、AさんはAIが作った骨子に、自社の強みや過去の成功事例、独自の視点を加えることで、オリジナリティのある企画書に昇華させました。AIのスピードと、人間の創造性や経験を組み合わせることで、一人でゼロから作るよりもはるかに質の高い成果物を生み出したのです。
AIの回答をコピーして貼り付けるだけでは、誰にでもできる仕事になってしまいます。そこから何を抽出し、どう編集し、自分のビジネスにどう結びつけるか。この最後の仕上げの部分で、その人のビジネスセンスや企画力が問われるのです。
チーム内に生まれる新たな「壁」
こうしたAIスキルの格差は、個人の生産性だけの問題に留まりません。チーム全体のコミュニケーションを阻害し、組織内に見えない壁を作ってしまう危険性も指摘されています。
AIを使いこなす人が高速でタスクをこなし、次々と新しいアイデアを出していく一方で、AIについていけない人は仕事の進め方が分からず、孤立感を深めてしまうかもしれません。「あの資料、AIでサッと分析しておいて」という指示が、ある人にとっては簡単な作業でも、別の人にとっては大きなストレスになるのです。
結果として、チーム内で知識や仕事の進め方に断絶が生まれ、協力し合うどころか、かえって全体のパフォーマンスが低下してしまう可能性すらあります。経営者やリーダーの皆さんは、ご自身の会社やチームで、こうした見えない分断が起きていないか、注意深く観察する必要があるでしょう。
これからの時代、AIとどう向き合うか
AIは、もはや一部の専門家だけが使う特殊なツールではありません。電卓やパソコンが当たり前になったように、これからのビジネスに不可欠な存在となっていくはずです。
大切なのは、AIに仕事を奪われると恐れることでも、AIを万能だと過信することでもありません。AIを、自分の能力を拡張してくれる賢いパートナーとして捉え、その付き合い方を学ぶことです。
今、AIを使いこなすための特別なスキルは、一部の人のものではなくなりました。誰もが学び、身につけることができる基本的なビジネススキルになりつつあります。
個人事業主の方も、中小企業の経営者の方も、まずは難しく考えずに、ChatGPTのような無料のツールから触れてみてください。そして、社員がいる場合は、社内で小さな勉強会を開いて、みんなでAIを試してみるのも良いでしょう。全員が専門家になる必要はありません。それぞれの立場で、自分の仕事にAIをどう活かせるかを考える。その一歩が、これからのAI格差の時代を乗り越えるための、大きな力になるはずです。
私も、皆さんと一緒に学びながら、AI活用のヒントを発信していきたいと思っています。一緒に新しい時代の働き方を模索していきましょう。

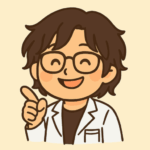
監修者:岡田 直記
AIコンサルント / 「ナオキのAI研究所」所長
企業のAI活用を支援するAIコンサルタント。セミナーや法人研修、個人指導などを通じ、これまでに延べ100名以上へAI活用の指導実績を持つ。現在は、主に中小企業を対象としたAI顧問として、業務効率化や生産性向上を実現するための戦略立案からツール導入までをサポート。また、個人向けには月額制の「AI家庭教師」サービスを展開し、実践的なAIスキルの習得を支援している。
自身の「元大手営業マンでスキル0から独立した」という異色の経歴を活かし、ビジネスの現場目線と最新のAI知識を組み合わせた、具体的で分かりやすい解説が強み。AI技術がもたらす未来の可能性を、一人でも多くの人に届けることを mission としている。