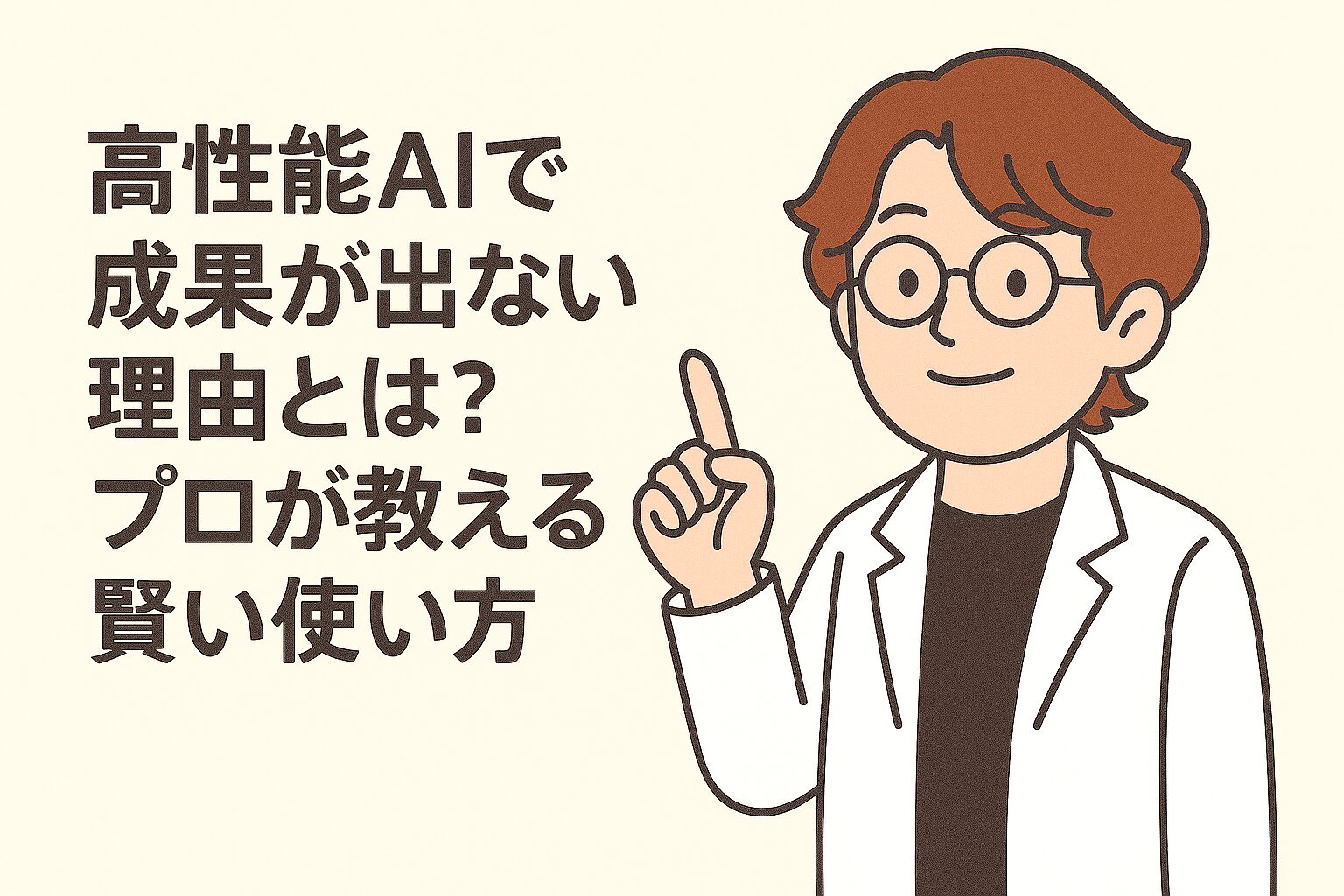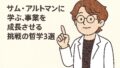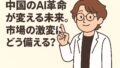AIを活用したビジネスの効率化をお手伝いしているナオキです。
皆さんは、最新のAIツールを導入してみたものの、なかなか思い通りの結果が出ずに「こんなはずじゃなかったのに」と首をかしげた経験はありませんか。特に、個人事業主や中小企業の経営者の皆さんにとっては、貴重な時間とコストを投資している分、その悩みは切実なものだと思います。
実は、月額で数万円もするような高性能なAIを使ったとしても、期待外れの結果に終わってしまうことは珍しくありません。これは決してAIの性能が低いからではなく、多くの場合、私たち人間の「使い方」に原因があるのです。
今日の記事では、なぜ最新のAIを使っても成果が出ないのか、その理由と、AIを真のビジネスパートナーにするための秘訣について、私の経験も交えながらお話ししていきたいと思います。
高性能AIが期待に応えてくれない二つの理由
「AIが自動で素晴らしい企画書を作ってくれる」「ボタン一つで売れるSNS投稿が完成する」そんなイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、現実は少し違います。うまくいかない背景には、大きく分けて二つの理由が隠されています。
理由①AIへの指示文が曖昧すぎる
一つ目の、そして最も大きな理由が、AIへの「指示文」、いわゆる「プロンプト」の質です。プロンプトとは、私たちがAIに「何をしてほしいのか」を伝えるための命令文のこと。これを、AIに対する「仕事の依頼書」だと考えてみてください。
例えば、新人のアシスタントに「ブログ記事、よろしく」とだけ伝えたらどうなるでしょうか。おそらく、どんなテーマで、誰に向けて、どのくらいの長さで書けばいいのか分からず、困ってしまうはずです。最悪の場合、見当違いの記事が出来上がってきて、書き直しをお願いする羽目になるでしょう。
AIもこれと全く同じです。「ブログ記事を書いて」という漠然とした指示では、AIも何を書けばいいのか判断できません。その結果、当たり障りのない、誰の心にも響かない文章が出来上がってしまうのです。
では、どうすれば良いのでしょうか。答えは、仕事の依頼書を具体的に書くことです。
悪い例「AIを使った業務効率化についてのブログ記事を書いて」
良い例「あなたはAI活用を専門とするコンサルタントです。読者はITに詳しくない中小企業の経営者。専門用語を避け、優しい言葉で、AI導入のメリットを伝えるブログ記事を書いてください。記事のテーマは『初めてのAI導入で失敗しないための三つのポイント』です。文字数は1500字程度で、読者の共感を呼ぶ導入から始めて、具体的な解決策を提示し、行動を促すまとめで締めくくってください」
ここまで具体的に指示を出すことで、AIはようやくあなたの意図を理解し、期待に近いクオリティのアウトプットを返してくれるようになります。月額3万円の高性能AIも、指示が曖昧ではその能力を十分に発揮できません。まさに「宝の持ち腐れ」になってしまうのです。
理由② AIが苦手な作業を無理に頼んでいる
もう一つの理由は、AIの得意不得意を理解せずに、苦手な作業を無理に頼んでしまっているケースです。AIは万能の魔法の道具ではありません。人間と同じように、得意なこともあれば、苦手なこともあります。
例えば、非常にニッチで専門的な業界の最新動向や、ごく一部のコミュニティでしか通用しないような暗黙の了解をAIに理解させるのは、今の段階ではまだ難しいでしょう。また、全くゼロから独創的なアイデアを生み出すといった、人間の深い洞察や経験に基づく創造性も、AIが苦手とする領域です。
私も以前、ある特定の業界に特化したSNS運用で、AIに投稿文のアイデアを出してもらったことがありました。しかし、出てくるのは一般的な内容ばかりで、業界の「あるある」ネタや専門家の心に刺さるような深い内容はなかなか生成できませんでした。結局、AIにはアイデアの壁打ち相手になってもらい、最終的な部分は自分の知識と経験で行うのが最も効率的だという結論に至りました。
AIに何でもかんでも任せようとせず、「この作業はAIに任せよう」「この部分は人間の判断が必要だ」といった見極めをすることが、AI活用の重要なポイントになります。
成功の鍵は「見えない努力」にある
では、どうすればAIをうまく使いこなせるようになるのでしょうか。その答えは、地道な「試行錯誤」にあります。AIはボタン一つで全てを解決してくれる魔法の杖ではありません。私たちが望む成果を得るためには、見えないところでの泥臭い努力が不可欠なのです。
何十回、何百回と指示を修正する地道な作業
私は独立した当初、AIを使いこなそうと必死でした。しかし、最初のうちは本当によく失敗しました。クライアントのウェブサイトに掲載する文章をAIに作ってもらっても、どこか機械的で心がこもっていない。そんな文章ばかりが出来上がりました。
「AIは使えないのかもしれない」と諦めかけたことも一度や二度ではありません。しかし、そこで私は考え方を変えました。一度の指示で完璧なものを求めず、何度も対話を繰り返しながら少しずつ理想に近づけていこう、と。
具体的には、最初に大まかな指示を出し、出てきた文章に対して「この部分の表現をもっと感情的にして」「読者が次に行動したくなるような一文を加えて」「別の例え話を使ってみて」といった形で、何度も修正の指示を重ねていきました。
それはまるで、職人が原石を少しずつ磨き上げて宝石にしていくような作業でした。何十回とプロンプトを修正し、試行錯誤を繰り返すうちに、AIのクセや最適な指示の出し方が感覚的に分かってくるのです。この地道な努力こそが、AIを単なるツールから強力なパートナーへと変えるための唯一の方法だと私は確信しています。
皆さんも、一度や二度の失敗で諦めてはいませんか。AIとの対話を楽しみながら、根気強く試行錯誤を続けてみてください。その先には、きっと素晴らしい成果が待っています。
AIはあなたの思考を映す鏡
今回は、最新のAIツールを使っても結果が出ない理由と、その解決策についてお話ししました。
高性能なAIであっても、私たちの指示が曖昧だったり、AIの苦手なことを無理に頼んだりしていては、その真価を発揮することはできません。大切なのは、AIを魔法の道具と考えるのではなく、粘り強く対話を重ねるべき「アシスタント」として捉えることです。
AIを使いこなすという行為は、単にツールを操作すること以上の意味を持ちます。それは、自分の考えを言語化し、課題を明確にし、解決策を具体的に指示するという、私たち自身の思考力を鍛える訓練でもあります。AIからの出力は、いわばあなたの思考を映す鏡なのです。
試行錯誤の過程は、決して楽な道のりではないかもしれません。しかし、その地道な努力の先にこそ、業務が劇的に効率化されたり、自分一人では思いつかなかったような新しいアイデアが生まれたりといった、大きな果実が実るのです。
私も、皆さんと一緒に学び、試行錯誤しながら、AIという頼もしい相棒と共にビジネスを成長させていきたいと思っています。この記事が、あなたのAI活用のヒントになれば幸いです。

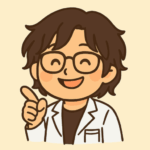
監修者:岡田 直記
AIコンサルント / 「ナオキのAI研究所」所長
企業のAI活用を支援するAIコンサルタント。セミナーや法人研修、個人指導などを通じ、これまでに延べ100名以上へAI活用の指導実績を持つ。現在は、主に中小企業を対象としたAI顧問として、業務効率化や生産性向上を実現するための戦略立案からツール導入までをサポート。また、個人向けには月額制の「AI家庭教師」サービスを展開し、実践的なAIスキルの習得を支援している。
自身の「元大手営業マンでスキル0から独立した」という異色の経歴を活かし、ビジネスの現場目線と最新のAI知識を組み合わせた、具体的で分かりやすい解説が強み。AI技術がもたらす未来の可能性を、一人でも多くの人に届けることを mission としている。