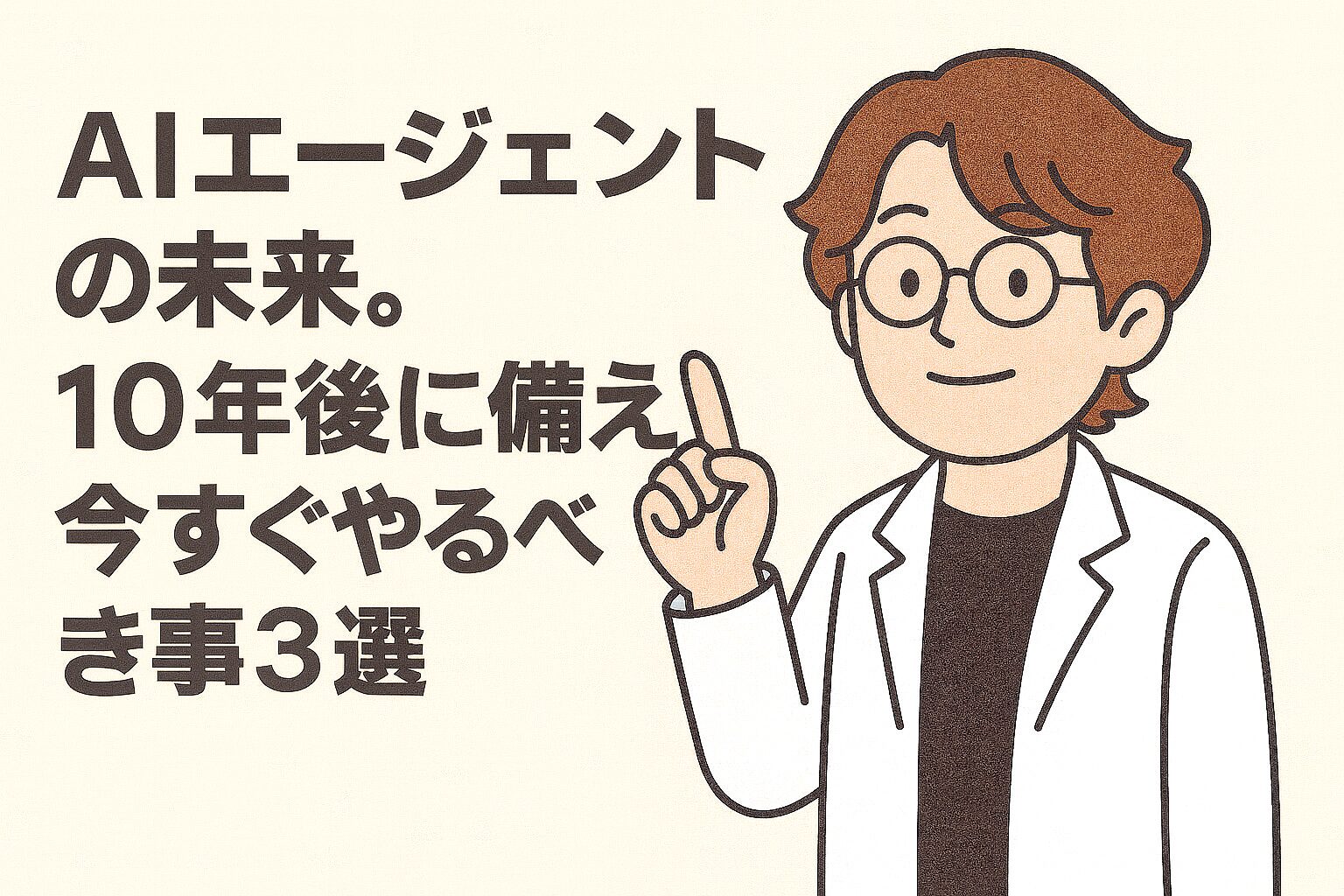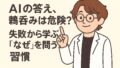AI活用の専門家ナオキです。個人事業主の方や中小企業の皆さんの業務効率化をお手伝いしています。
最近、クライアントの皆さんから「AIがどんどん進化していて、どこまで追いかければいいのか分からない」という声をよく聞きます。特に今年は「AIエージェントの年になる」なんて言葉も飛び交い、期待と同時に少し焦りを感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
AIエージェントとは、私たちが指示を出すと、自律的に考えてタスクを最後までやり遂げてくれる、まるで優秀な秘書のようなAIのことです。これが実現すれば、私たちの働き方は劇的に変わるかもしれません。
しかし、本当にその「元年」は今年なのでしょうか。この点について、AI分野の第一人者であるアンドレイ・カルパシー氏が非常に興味深い見解を示しています。今回は彼の言葉をヒントに、私たちがこれからAIの進化とどう向き合っていくべきか、一緒に考えていきたいと思います。
そもそもAIエージェントって何?
本題に入る前に、まずは「AIエージェント」という言葉について、簡単におさらいしておきましょう。少し専門的に聞こえるかもしれませんが、イメージとしては「自ら考えて行動するAIアシスタント」です。
今のChatGPTのような対話型AIは、私たちが質問や指示を一つ出すと、それに対して一つの答えを返してくれます。とても賢いのですが、基本的には「指示待ち」の状態です。
それに対してAIエージェントは、もっと能動的に動きます。例えば、あなたが「来週の東京出張、予算内で効率的な新幹線とホテルを予約しておいて」と指示したとします。するとAIエージェントは、自分で複数の予約サイトを比較検討し、最適な新幹線のチケットを購入し、評判の良いホテルを予約し、あなたのカレンダーに予定まで登録してくれる、といった一連の作業を自動でこなしてくれるのです。
まさに、夢のような話ですよね。SNS運用に活用すれば、ターゲット層に合わせた投稿内容の企画から作成、投稿予約までを自動化してくれるかもしれません。CRMと連携させれば、見込み顧客への最適なタイミングでのアプローチを自動で行ってくれる、なんて未来も考えられます。
専門家が語る「AIエージェントの10年」という視点
このように大きな可能性を秘めたAIエージェントですが、前述のアンドレイ・カルパシー氏は、「今年はAIエージェントの年になる」という見方には慎重です。彼は、これは「AIエージェントの10年」の始まりと捉えるべきだと語っています。
カルパシー氏は、かつてテスラでAI部門を率い、現在はChatGPTを開発したOpenAIで活躍する、まさにAI開発の最前線にいる人物です。その彼がなぜ、短期的な進化に慎重な見方を示しているのでしょうか。
なぜ「10年」という長い時間が必要なのか
その理由は、現在のAI技術にはまだ解決すべき課題が多く残されているからです。
今のAIは、一つの特定の作業、例えば文章を書いたり、プログラムのコードを生成したりするのは非常に得意です。しかし、AIエージェントがこなすべき複雑なタスクは、そうした小さな作業の組み合わせで成り立っています。
先ほどの出張手配の例で考えてみましょう。このタスクには、「最適な移動手段を探す」「複数の予約サイトを比較する」「空席や空室を確認する」「決済情報を入力する」「予約完了メールを確認する」「カレンダーに登録する」といった、たくさんのステップが含まれています。
現在のAIは、こうした複数のステップを正確に、そして臨機応応変にこなすのがまだ苦手なのです。例えば、予約サイトのデザインが少し変わっただけでエラーを起こしてしまったり、予期せぬ確認画面が出たことでフリーズしてしまったりすることがあります。また、それぞれのツールやサービスをスムーズに連携させるための技術も、まだ発展途上です。
私自身も、業務自動化のために様々なAIツールを試していますが、やはり最後の確認作業や、AIが途中で止まってしまった際の原因究明など、まだまだ人の手が必要だと感じる場面は少なくありません。皆さんも、AIに仕事を任せてみたら、かえって手間が増えてしまった、という経験はありませんか。
こうした課題を一つひとつ解決し、AIが本当に信頼できる「秘書」になるためには、地道な研究と開発が不可欠です。だからこそ、カルパシー氏は一過性のブームとしてではなく、10年という長いスパンで着実に進化していくトレンドだと捉えているのです。
では、私たちは今どう向き合うべきか
「なんだ、実用化はまだ先の話か」とがっかりされたかもしれません。しかし、「10年かかるから、今はまだ関係ない」と考えるのは、非常にもったいないことです。むしろ、この長期的なトレンドを理解した上で、今から準備を始めることこそが、未来のビジネスを大きく左右します。
では、具体的に私たちは何をすればよいのでしょうか。
1. 現在のAIツールを使いこなす
まずは、今あるAIツールに慣れ親しむことが大切です。ChatGPTやCopilotなどを積極的に業務に取り入れてみましょう。AIエージェントは、こうした対話型AIの延長線上にある技術です。今のうちからAIとの対話や、的確な指示を出すスキルを磨いておくことは、将来必ず役立ちます。
例えば、クライアントへのメールの文章をAIに下書きしてもらったり、会議の議事録を要約させたり、新しい企画のアイデアを出してもらったりと、できることはたくさんあります。小さな成功体験を積み重ねて、AIを「使う」感覚を養っておきましょう。
2. 業務のデジタル化と整理を進める
AIエージェントが真価を発揮するためには、AIがアクセスできる「整ったデータ」が不可欠です。AIに仕事を任せたいと思っても、必要な情報が紙の書類や担当者の頭の中にしかない、という状態では、AIも動きようがありません。
今のうちから、社内の情報をデジタル化し、整理しておくことを強くお勧めします。例えば、顧客情報はCRMシステムで一元管理する、業務マニュアルをオンラインで整備するなど、AIが活躍しやすい環境を整えておくのです。これはAI活用だけでなく、業務全体の効率化にも直結します。あなたの会社では、新入社員でも迷わずに業務を進められるくらい、情報や手順が整理されていますか。まずはそこから見直してみるのも良いでしょう。
3. 過度な期待をせず、最新情報を追い続ける
AIの進化のスピードは、時に私たちの想像を超えます。だからといって、あらゆる新技術に飛びつく必要はありません。過度な期待で一喜一憂するのではなく、「自分のビジネスにどう活かせるか」という視点を持ちながら、冷静に最新情報をキャッチアップしていく姿勢が重要です。
このブログでも、皆さんのビジネスに役立つAIの最新情報や具体的な活用方法を、これからも分かりやすく発信していきますので、ぜひ参考にしてください。
まとめ
今回は、AIエージェントの未来について、専門家の見解を交えながらお話ししました。
AIエージェントが私たちの働き方を大きく変える可能性は非常に高いですが、それは一夜にして起こる革命ではありません。今後10年かけてじっくりと進んでいく、大きな大きな潮流なのです。
大切なのは、この流れに乗り遅れることを焦るのではなく、今自分たちの足元を固め、着実に準備を進めていくことです。現在のAIツールに慣れ、業務のデジタル化を進めておくこと。この地道な一歩が、数年後、ライバルとの大きな差を生むはずです。
10年後の未来を見据えて、今できることから一緒に始めていきませんか。

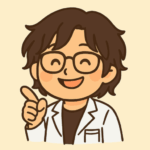
監修者:岡田 直記
AIコンサルント / 「ナオキのAI研究所」所長
企業のAI活用を支援するAIコンサルタント。セミナーや法人研修、個人指導などを通じ、これまでに延べ100名以上へAI活用の指導実績を持つ。現在は、主に中小企業を対象としたAI顧問として、業務効率化や生産性向上を実現するための戦略立案からツール導入までをサポート。また、個人向けには月額制の「AI家庭教師」サービスを展開し、実践的なAIスキルの習得を支援している。
自身の「元大手営業マンでスキル0から独立した」という異色の経歴を活かし、ビジネスの現場目線と最新のAI知識を組み合わせた、具体的で分かりやすい解説が強み。AI技術がもたらす未来の可能性を、一人でも多くの人に届けることを mission としている。