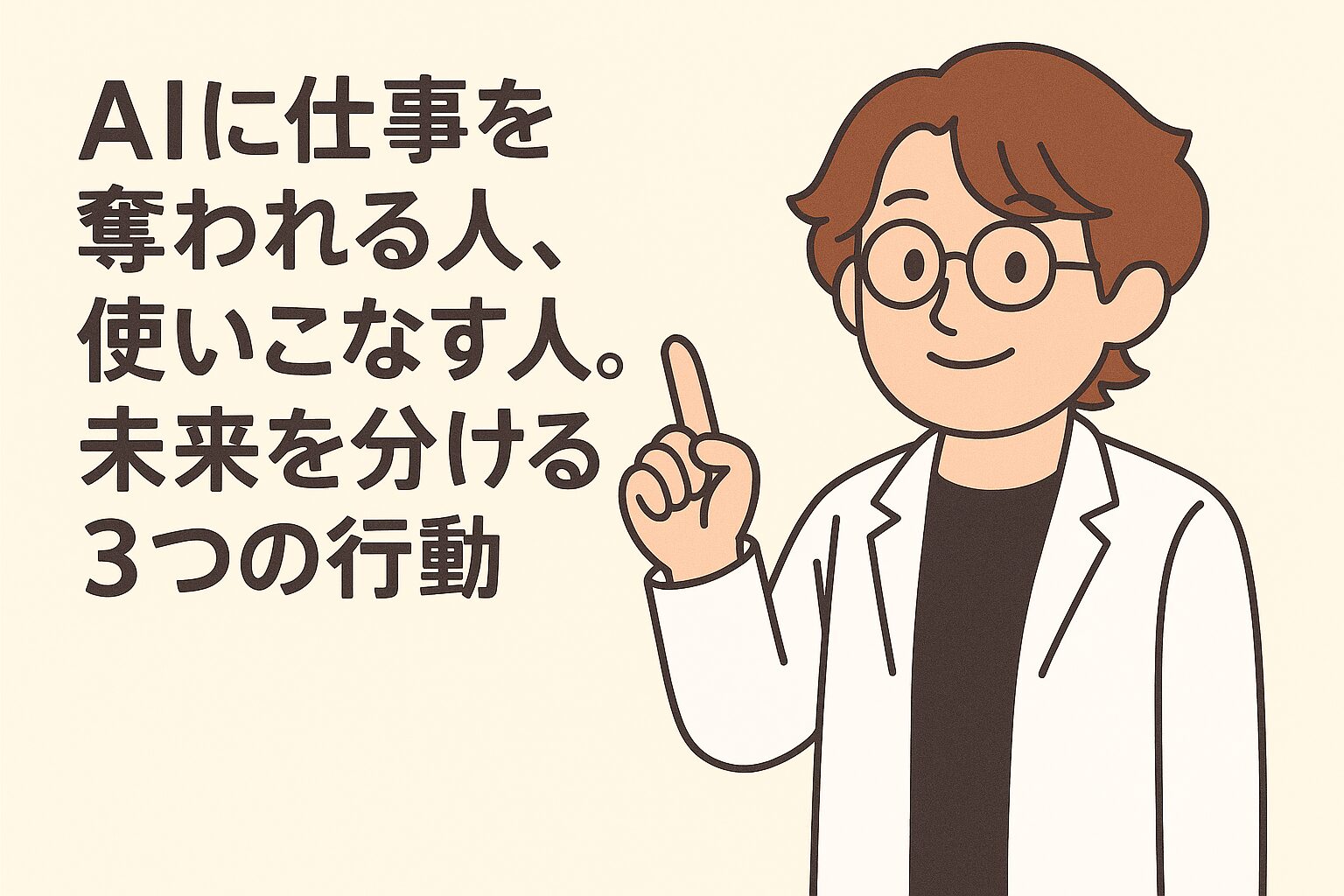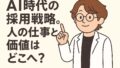AI活用の専門家ナオキです。
最近、クライアントの方々とお話ししていると、「AIで仕事がなくなるって本当ですか?」という質問をよくいただきます。少し前までは未来の話のように聞こえましたが、今やその変化はすぐそこまで来ています。
今回は、スウェーデンの決済サービス企業「Klarna(クラルナ)」が示した少し衝撃的な未来予想図をもとに、AIが私たちの働き方にどのような影響を与えるのか、そして私たちはどう向き合っていくべきなのかを一緒に考えていきたいと思います。
AI導入で従業員が半分以下に、Klarna社で起きたこと
まず、Klarna社で何が起こったのかを見ていきましょう。この会社は、AIを積極的に業務に取り入れた結果、従業員の数が7,400人から3,000人へと、半分以下にまで減少したと発表しました。
この話だけ聞くと、「大規模なリストラがあったのでは?」と不安に思うかもしれません。しかし、驚くべきことに、これは解雇によるものではないのです。同社によると、退職した従業員のポジションを補充せず、その業務をAIに任せることで、自然な形で人員の削減を実現したとのこと。つまり、人が辞めた穴を、新しい人ではなくAIが埋めていったわけです。
CEOが鳴らす警鐘「AIの影響を甘く見ている」
さらに注目すべきは、同社のCEOが発した警告です。「多くの企業は、AIがビジネスに与える影響を過小評価している」と彼は語ります。
彼の言葉は、AIが単に私たちの仕事を「手伝う」便利なアシスタントではなく、既存の仕事を丸ごと「置き換える」力を持っていることを示唆しています。これまで私たちが当たり前だと思っていた業務の多くが、近い将来、AIによって自動化される可能性は非常に高いのです。
これは、遠い海外の大企業だけの話ではありません。この自動化の波は、間違いなく日本の、それも私たちのような個人事業主や中小企業の働き方にも大きな影響を与えていくでしょう。
なぜ他人事ではないのか?中小企業への影響
「うちは大企業じゃないから関係ない」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実はリソースが限られている中小企業や個人事業主こそ、この変化と真剣に向き合う必要があります。
AIが得意な仕事とは?
Klarna社の事例で自動化されたのは、主にカスタマーサポートやマーケティング関連の業務だったと言われています。AIが得意とするのは、ルールに基づいた定型的な作業や、大量のデータを分析してパターンを見つけ出すことです。
あなたのビジネスを少し振り返ってみてください。
- 毎日のように送っている定型的なメールの返信
- SNSの投稿文の作成や予約投稿
- 顧客からの簡単な問い合わせ対応
- 請求書や見積書の作成
- Webサイトのアクセス解析レポートの作成
いかがでしょうか。もし、このような作業に多くの時間を費やしているのであれば、それらは近い将来AIに任せられるようになる可能性が高い業務と言えます。
「効率化」の先にある「代替」
これまで私たちは、AIを「業務効率化ツール」として捉えてきました。「面倒な作業はAIに任せて、人間はもっと創造的な仕事に集中しよう」という考え方です。私自身も、常々そのようにお伝えしてきました。
しかし、Klarna社の事例は、その「効率化」が極限まで進むと、業務そのものが人間を必要としなくなる「代替」のフェーズに入る可能性を示しています。
例えば、最初はSNSの投稿案をAIに作ってもらうだけだったのが、次第にAIが最適な投稿時間を分析し、自動で投稿し、その結果を分析して次の改善案まで提案してくれるようになったらどうでしょう。そこにはもう、人間の「作業」が入る余地はほとんどなくなってしまいます。
では、私たちはどうすればいいのか?
ここまで読むと、AIに対して恐怖心や不安を抱いてしまうかもしれません。しかし、いたずらに怖がる必要はありません。大切なのは、この変化を正しく理解し、今から備えることです。
これは、かつて自動車が登場したことで馬車の御者の仕事がなくなった一方で、自動車整備士や運転手といった新しい仕事が生まれたのと同じ構造です。変化の波に飲み込まれるのではなく、その波を乗りこなす側に回るための準備を始めましょう。
今すぐできる3つのアクション
では、具体的に何をすればいいのでしょうか。私がおすすめする、今すぐ始められる3つのことをご紹介します。
- まずはAIを「触って」みる
何よりも大切なのは、実際にAIを使ってみることです。ChatGPTや画像生成AIなど、今では無料で高性能なAIツールがたくさんあります。まずは遊び感覚で構いません。「自社の新商品のキャッチコピーを10個考えて」「ブログ記事の構成案を作って」など、自分の仕事に関連することでAIに話しかけてみてください。使ってみることで、AIの得意なこと、苦手なことが肌感覚で分かり、自分の仕事にどう活かせるかのヒントが見つかります。 - 自分の仕事内容を「分解」してみる
次に、ご自身の業務を棚卸ししてみてください。そして、その業務を「AIに任せられそうな単純作業」と、「人間にしかできない付加価値の高い仕事」に分けてみましょう。
例えば、顧客との信頼関係を築くための雑談や深いヒアリング、前例のない課題に対する解決策の立案、ビジネスの未来を描くビジョン策定などは、まだまだ人間にしかできない領域です。自分の強みや価値がどこにあるのかを再認識することが、AI時代を生き抜く羅針盤になります。 - AIを「使いこなす」スキルを学ぶ
これからの時代に求められるのは、AIに仕事を奪われる人ではなく、AIを道具として使いこなせる人です。AIに的確な指示を出す「プロンプト」の技術や、複数のAIツールを連携させて業務フロー全体を自動化する知識は、強力な武器になります。言わば、AIという新しい部下を上手にマネジメントするスキルを身につけるということです。
まとめ
Klarna社の事例は、私たちにAIがもたらす未来の一端をはっきりと見せてくれました。それは、人によっては脅威に映るかもしれません。しかし、見方を変えれば、これは大きなチャンスです。
これまで単純作業に追われていた時間から解放され、私たちが本当にやりたかったこと、つまりお客様と向き合う時間や、新しいサービスを考える時間、自分自身のスキルアップに使う時間を手に入れられる可能性を秘めているのです。
「AIに仕事を奪われる」未来ではなく、「AIを使って新しい価値を生み出す」未来へ。その分かれ道は、今、この瞬間からAIとどう向き合うかにかかっています。
この記事が、あなたのビジネスと働き方の未来を考えるきっかけになれば幸いです。もし、ご自身のビジネスで具体的にどうAIを活用すればいいか分からない、といったお悩みがあれば、いつでもお気軽にご相談くださいね。一緒に新しい時代を乗りこなしていきましょう。

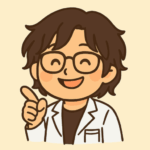
監修者:岡田 直記
AIコンサルント / 「ナオキのAI研究所」所長
企業のAI活用を支援するAIコンサルタント。セミナーや法人研修、個人指導などを通じ、これまでに延べ100名以上へAI活用の指導実績を持つ。現在は、主に中小企業を対象としたAI顧問として、業務効率化や生産性向上を実現するための戦略立案からツール導入までをサポート。また、個人向けには月額制の「AI家庭教師」サービスを展開し、実践的なAIスキルの習得を支援している。
自身の「元大手営業マンでスキル0から独立した」という異色の経歴を活かし、ビジネスの現場目線と最新のAI知識を組み合わせた、具体的で分かりやすい解説が強み。AI技術がもたらす未来の可能性を、一人でも多くの人に届けることを mission としている。