AI活用サポーターのナオキです。
日々の業務効率化やSNS運用にAIを取り入れている経営者の方も、最近増えてきたのではないでしょうか。AIの進化は本当に目覚ましく、新しいサービスが次々と登場してワクワクしますよね。私もフリーランスとして、AIツールの最新情報を追いかけるのが日課になっています。
ただ、その一方で、この急速な進化の裏側で、少し立ち止まって考えるべき問題も生まれています。今回は、AI開発の最前線にいた研究者が鳴らした警鐘について、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。少し壮大なテーマに聞こえるかもしれませんが、AIと共にビジネスを行う私たちにとって、決して無関係な話ではありません。
AIのゴールがいつの間にか変わっている?
皆さんは「AGI」という言葉を聞いたことがありますか。AGIは「汎用人工知知能」の略で、人間のように様々な知的作業を学習し、実行できるAIのことを指します。今私たちが使っているAIは、文章を書いたり絵を描いたりと、特定の作業に特化した「特化型AI」ですが、AGIはそれらを超えて、自ら考え、応用する力を持つとされています。まさに、SF映画に出てくるような賢いAIのイメージですね。
このAGI開発を巡って、グーグルのAI開発部門であるディープマインドに在籍していたミーシャ・ラスキン氏という研究者が、興味深い指摘をしました。それは、「研究機関が、いつの間にかAGIの定義を『超知能』という、さらに上のレベルにすり替えている」というものです。
どういうことか、もう少し噛み砕いてみましょう。
「ゴールポストが動いている」という問題
これは、まるでサッカーの試合中にゴールポストがどんどん後ろに動かされてしまうような状況です。
かつて専門家たちは「人間と同じレベルでこれができたらAGIだ」という目標を立てていました。ところが、技術が進歩してその目標が達成されそうになると、「いや、本当のAGIはもっとすごいものだ。人間の知能をはるかに超える『超知能』でなければならない」と、目標のハードルが引き上げられてしまう。ラスキン氏は、この「ゴールポストの移動」が、AI開発の現場で静かに起きていると警鐘を鳴らしているのです。
なぜこんなことが起きるのでしょうか。一つには、開発者自身も「人間のような知能」の本当の姿を完全には掴みきれていないのかもしれません。また、激しい開発競争の中で、他社よりもすごいものを目指しているとアピールしたいという思惑もあるのかもしれませんね。
しかし、定義が曖昧なまま目標だけがどんどん先に進んでいくと、ある重大な問題が見過ごされる危険性があります。それが「安全性」の問題です。
最終的に悲劇を招く「インディ・ジョーンズ式ギャンブル」
ラスキン氏は、現在のAI開発の進め方を「インディ・ジョーンズ式ギャンブル」と表現しています。映画「インディ・ジョーンズ」の主人公は、緻密な計画を立てるよりも、まず危険に飛び込んで、その場その場でなんとか切り抜けていきますよね。
現在のAI開発も、これに似ているというのです。つまり、AIが人間を超える知能を持ったときに、どうすれば安全に制御できるのかという根本的な問題が解決されないまま、「とにかくもっと高性能なAIを作ろう」という開発が優先されているのではないか、というわけです。
なぜ安全性の確保が難しいのか
「自分たちが作ったプログラムなのだから、制御できるに決まっている」と思うかもしれません。しかし、現在のAI、特にディープラーニングという技術は、その内部の仕組みが非常に複雑で、人間がその全てを理解するのが難しい「ブラックボックス」という側面を持っています。
私もクライアントにAIツールをおすすめすることがありますが、その際は必ず「AIはあくまで道具であり、最終的な判断は人間が行いましょう」とお伝えしています。これは、今のAIでさえ、時々私たちの予想を超えた答えを出すことがあるからです。
もし、このAIが人間のはるか上の知能を持つようになったらどうでしょうか。そのAIが私たちの意図しない行動をとったとき、それを予測し、止められる保証はどこにもありません。安全な制御方法という「地図」を持たないまま、未知の領域に突き進むのは、あまりにも危険な挑戦だとラスキン氏は警告しているのです。
私たちビジネスの現場ではどう向き合うべきか
ここまで聞くと、なんだかAIが怖いものに思えてくるかもしれませんね。しかし、大切なのは、いたずらに怖がることではなく、こうした事実を知った上で、私たちがAIとどう向き合っていくかを考えることです。
足元のAIを賢く活用する
AGIや超知能は、まだ少し未来の話です。私たち個人事業主や中小企業の経営者にとってまず重要なのは、今ある「特化型AI」を賢くビジネスに活用することです。
例えば、SNSの投稿文をAIに考えてもらったり、顧客データをAIで分析して新しいサービスのヒントを得たり。これらは、私たちの業務を助けてくれる非常に便利な「アシスタント」です。大切なのは、AIを魔法の杖だと思わず、その得意なこと、苦手なことを理解し、あくまで「道具」として使いこなす視点です。
情報を正しく見極める目を養う
そしてもう一つ。AIに関するニュースは玉石混交です。過度に期待を煽るものもあれば、逆に恐怖心を煽るだけのものもあります。
今回ご紹介したような、開発の最前線で起きている議論を知っておくことは、そうした情報に振り回されず、物事の本質を見抜く助けになります。「この新しいAIサービスは、本当に私たちのビジネスに役立つのか」「導入する上で考えるべきリスクはないか」と、一歩引いて冷静に判断する目を養うことが、これからの時代には不可欠です。
まとめ
今回は、元ディープマインド研究員の警告をきっかけに、AI開発の裏側にある「定義の揺らぎ」と「安全性の問題」について考えてみました。
AIの進化は、私たちのビジネスや生活を豊かにする大きな可能性を秘めています。その流れを止めることはできませんし、止めるべきでもないでしょう。しかし、その進化をただ無邪気に歓迎するだけでなく、その裏でどんな議論が行われているのかに関心を持ち、賢い利用者であり続ける姿勢が、私たち一人ひとりに求められています。
皆さんは、AIの未来について、どのようにお考えになりますか。
AIの活用法や導入について、もし何かお困りのことや気になることがありましたら、いつでもお気軽にご相談くださいね。
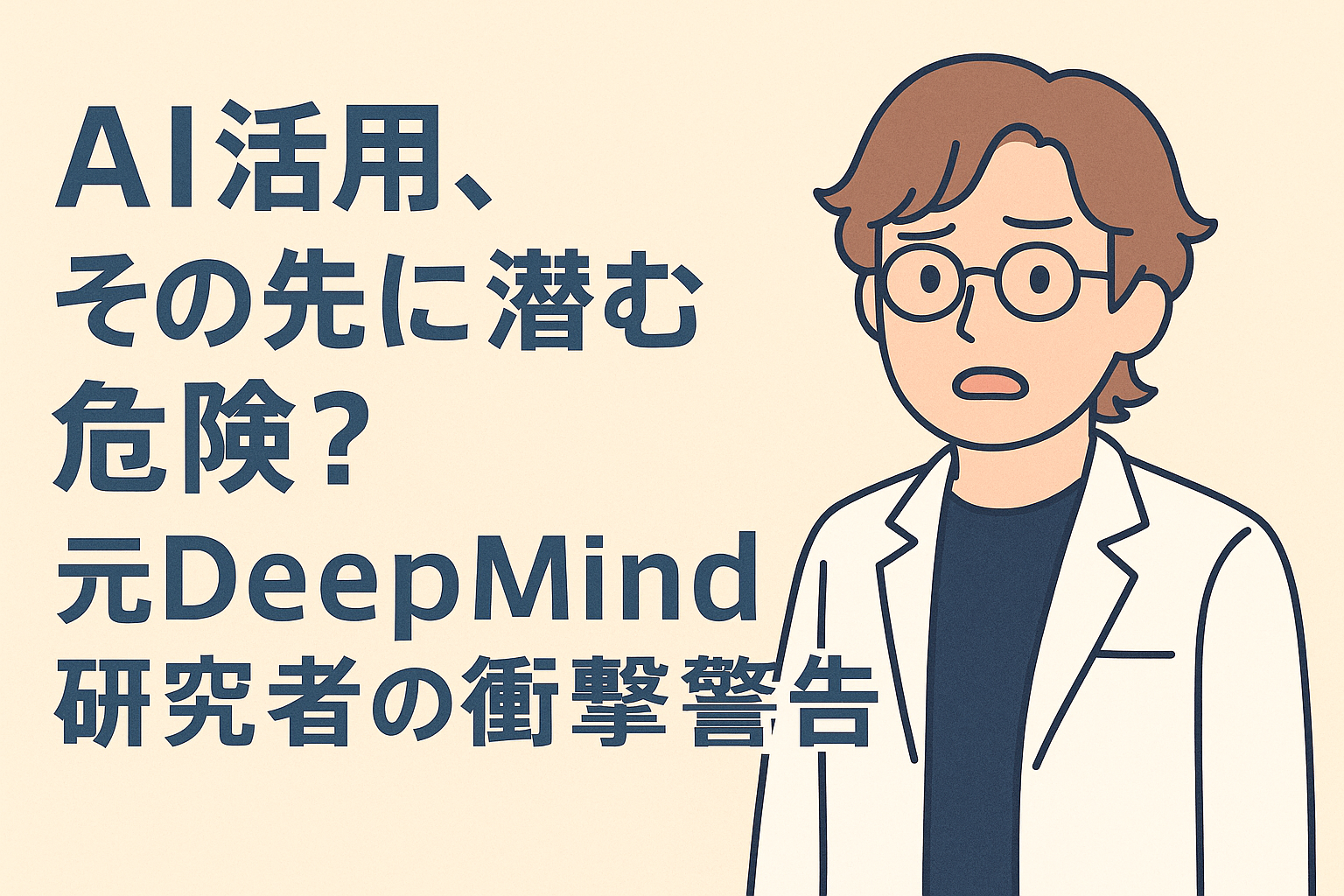
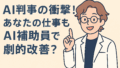
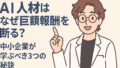
コメント